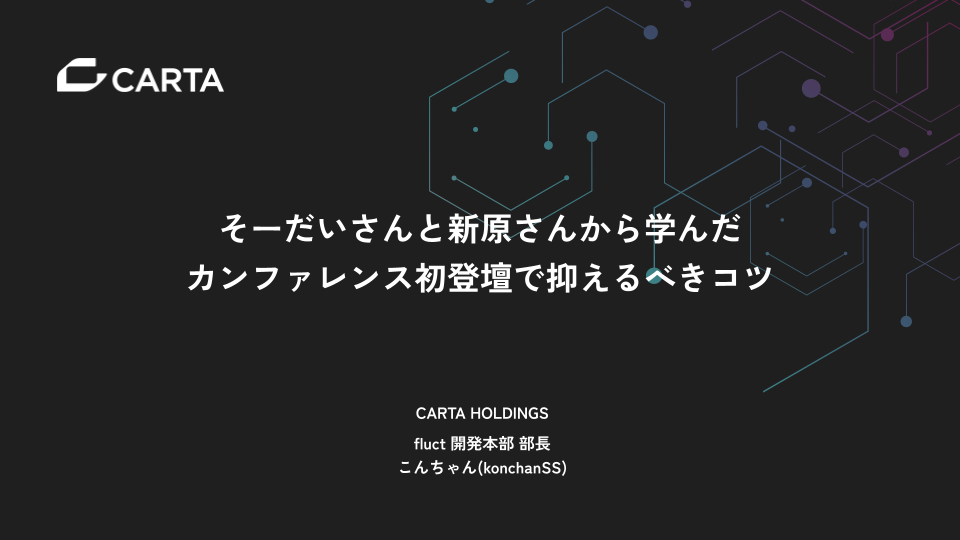こんにちは、株式会社fluctのこんちゃんです。
私は2025年5月31日(土)に開志専門職大学 米山キャンパスで開催された
PHPカンファレンス新潟2025で登壇しました。
登壇資料は下記になります。
今回はそーだいさんと新原さんに教わった登壇で抑えるべきコツをご紹介します。
背景と経緯
CARTAは4年以上前からそーだいさんに技術顧問としてCARTA全体に対してサポートしていただいています。また、去年からは新原さんも技術顧問としてfluctのアドバイザーをしていただいています。
そのような背景から私が初登壇だったのもあり、登壇経験豊富な2人にアドバイスをもらいながら登壇資料を作成していきました。
その中で学んだこと、そーだいさんと新原さんにフィードバックされた内容をまとめてみました。
実例を交えながら、登壇で抑えるべきコツについて話していきます。
特にそーだいさんに関しては4回ほど一緒に登壇資料の見直しをしていただき感謝しかないです。
登壇のコツ
ずばりコツは4つあります。
- 聴衆に最初に理想の形を見せるべし
- 具体と抽象が交互に来るようにするべし
- 本番で何があっても良いように、これだけは話したいを先に決めるべし
- 資料作成で迷ったら話したいことを絞るべし
では、それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 聴衆に最初に理想の形を見せるべし
料理番組で今から麻婆豆腐を作りますと言ってから作りはじめるように最初にゴールのイメージを与えてあげることで聴衆が話に入りやすくなるよ by そーだい
1つ目の教えは「聴衆に最初に理想の形を見せるべし」 です。
登壇の最初に事業背景や言葉の定義を先に聴衆に説明しておくことで実際に具体例やその言葉が出てきたときに聴衆がスッと理解しやすくなります。
それと同じで問題提起から解決の過程を話す前にまずは理想の形を聴衆に見せることでこれから話すことは理想の形に向かうための過程と理解した状態で話を聞くことができる効果があります。
そーだいさんの実際の登壇資料も最初にゴールのイメージやゴールに向かう理由を話してから
本題に入るケースが多く、これは登壇経験が多いそーだいさんだからこそ言えることだと思います。
2. 具体と抽象が交互に来るようにするべし
具体の話をしたら、抽象の話をする。逆も然りで抽象の話のあとは具体の話をするといいよ by そーだい
聴衆に話している現在地を示すために定期的に具体例を交えながら話すといいですよ by 新原
2つ目の教えは「具体と抽象が交互に来るようにするべし」 です。
登壇は聴衆と一緒に作り上げるもので、登壇の目的は聴衆の明日の行動を変えることです。
登壇において抽象化して話すことは、それを聞いた聴衆が実際の現場で当てはめて聞きやすくなるので大事です。
その一方で抽象的な話に終始してしまうと結局何をすればいいんだっけ?というのが聴衆に丸投げしたままの状態になってしまい聴衆が実践しづらいものになってしまいます。
なので、具体と抽象が必ず交互になるように話すことで聴衆が現場に落とし込んで実践しやすいものになります。
また、抽象的な話が長くなる場合は間に具体例を示すことで聴衆が迷子になりづらくなります。
3. 本番で何があっても良いように、これだけは話したいを先に決めるべし
練習時にどのスライドで何分使ったかを測って、当日押したときはここだけは話したいを決めておくといいよ by そーだい
3つ目の教えは「本番で何があっても良いように、これだけは話したいを先に決めてべし」 です。
登壇練習では与えれた時間通り話ができても本番では緊張など様々な要因で練習通りにいかないのはあるあるです。
私の場合、初登壇だったので想定外のことは必ず起きるだろうと思っていました。
その対策として登壇練習時に各スライドに何分使ったかをスピーカーノートにメモしておくことで
登壇中の時間管理で予定の時間を過ぎている、もしくは早すぎる場合のペースコントロールに利用するというのを教わりました。
また、登壇において自分が言いたいこと、自分だから言えることは必ず伝えたいですよね。
なので、これだけは話したいことを先に決めておいて、どうしても収まらない場合はそれ以外の章を飛ばすという意思決定を先にしておくのが大事だと教わりました。
そーだいさんに以前以下の登壇資料をCARTAで再演してもらったことがありました。
登壇時間10分というかなりの無茶振りでしたが、そーだいさんは資料はそのままにスライドを飛ばしながらちゃんと伝えたいことは伝えていたのが印象に残っています。
これも登壇経験が豊富なそーだいさんだからこそ言えることだと思います。
4. 資料作成で迷ったら話したいことを絞るべし
迷っているときは大体、話したいことが多すぎる時におきます by 新原
4つ目の教えは「資料作成で迷ったら話したいことを絞るべし」 です。
登壇の機会をもらっていざ資料を作り始めると思った以上に進捗が出せないことがありますよね。
その際に大事なのは伝えたいメッセージを1つに絞ることです。
資料作成で悩んでいるとき多くは、伝えたいメッセージを散りばめすぎていて聴衆に与える情報量が膨大になっていることが原因にあります。
PHPカンファレンスのレギュラートークの20分枠は一見長く見えますが、複数のメッセージを伝えるには短いと教わりました。
また、1番伝えたいメッセージは何かを決めることが大事だと教わりました。
これも登壇経験豊富な新原さんならではのアドバイスだと思います。
この新原さんの言葉が資料作成初期の僕にとっては金言だったので、登壇資料作成用のGoogle Docsの一番上に貼って常に見えるようにしていました。
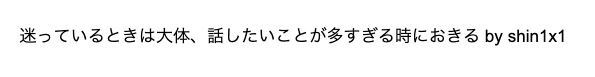
まとめ
今回はそーだいさんと新原さんから学んだ初登壇で抑えるべきコツをまとめました。
そーだいさんと語録と新原さん語録をまとめてみましょう。
どれもお二人だからこそ言えることでとても響きました。
そーだいさん語録
- 料理番組で今から麻婆豆腐を作りますと言ってから作りはじめるように最初にゴールのイメージを与えてあげることで聴衆が話に入りやすくなるよ
- 具体の話をしたら、抽象の話をする。逆も然りで抽象の話のあとは具体の話をするといいよ
- 練習時にどのスライドで何分使ったかを測って、当日押したときはここだけは話したいを決めておくといいよ
新原さん語録
- 聴衆に話している現在地を示すために定期的に具体例を交えながら話すといいですよ
- 迷っているときは大体、話したいことが多すぎる時におきます
この記事が登壇する人にとって役に立てばとても嬉しいです。