
技術広報しゅーぞーです。CARTAHOLDINGSは技育祭2025春に協賛し、ブース出展に加えて登壇も行いました!今回は「CARTA登壇の全文文字起こし」をお届けします!
スライド
タイトル : AIは脅威でなくチャンス。 AIと共に進化するエンジニアの成長戦略
登壇者 : CARTA全社CTO: @suzu_v
概要
AIの登場で不安を感じる学生も多いでしょう。むしろ大きなチャンスです。AIはプロトタイピングを容易にし、学習を劇的に加速する強力なツールです。本講演では、2025年の技術環境とCARTAの実際の開発事例を交えながら、AIと共に進化するエンジニアの成長戦略をお伝えします。
AIは脅威でなくチャンス。 AIと共に進化するエンジニアの成長戦略
自己紹介とCARTA HOLDINGSの概要

はい、どうもよろしくお願いいたします。初めての技育祭ということで大変楽しみにしてまいりました。今日は「AIは脅威ではなくチャンス:AIと共に進化するエンジニアの成長戦略」というテーマで、CARTA HOLDINGSのCTO鈴木健太が話をさせていただきます。皆さん今日はどうぞよろしくお願いします。

簡単に自己紹介しますと、2012年にCARTAに新卒で入社しまして、その頃からバックエンドやデータエンジニアリングの領域を担当していました。私自身はバックエンドドメインで広告領域のエンジニアリングを主にやってきたんですけれども、そんな中で事業のCTOをやったりとか、プロダクトに没頭するということをやっております。現在はCARTA HOLDINGSという会社で、全体のCTOを務めています。書籍を書いたり、データ基盤を作るみたいなことをやっていますが、今は主に組織マネジメントや技術戦略を立てて、経営陣としてコミットするようなことをやっております。
はい。では、CARTAについて簡単に説明しようと思います。事業は20以上あります。サポーターズもCARTAの一つの事業となっています。エンジニアは170人以上在籍しており、オフィスはここです。オフラインで参加されている皆さんは、今まさにCARTAのオフィスにいらっしゃいます。よろしくお願いします。オンラインの方々は、今画面に映っているのがCARTAのオフィスとなります。
これまでのエンジニアリングの在り方は終わり、新しい在り方に
今日の発表のテーマについてお話しします。このように多くの事業があり、多くのエンジニアが在籍している中で、社内のエンジニアも同じようなことを考えています。
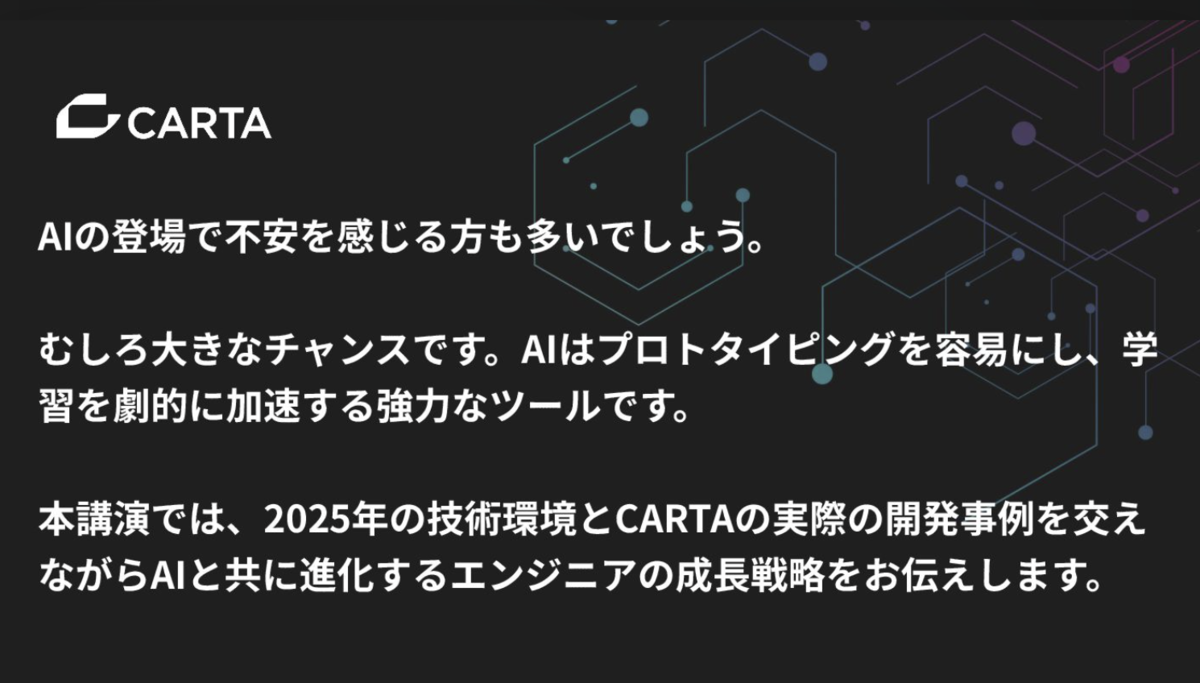
AIが登場して不安を感じる方も多いでしょう。「自分たちの仕事はどうなるのだろう」と思うプログラマーも多いと思います。しかし、これは 大きなチャンスです。AIはプロトタイピングを容易にし、学習を劇的に加速する強力なツールだと考えています。 本講演では、2025年の技術環境とCARTAの実際の開発事例を交えながら、AIと共に進化するエンジニアの成長戦略をお伝えします。
はい。ちょっと簡単な質問を皆さんにさせてください。皆さんはAIの登場でプログラミングがどう変わると思いますか?変わると思う人、手を挙げてもらえますか?お、ありがとうございます。ちなみに、もうAIが出る前と比べてプログラミングが全然変わっちゃったよって人はどれくらいいますか?もうすでに変わったと感じている人。あ、ありがとうございます。
会場の7割くらいがAIとともにプログラミングしているエンジニアですね。この世代はオンラインは3人しか手を挙げていないので、オンラインよりも圧倒的に会場にいる皆さんのほうがAIを活用している人が多いかもしれませんね。そうですね、めちゃくちゃ変わりましたよね。皆さんはこれから就職する方が多いと思いますが、本当にこのAIにネイティブに触れ、共に成長してきたエンジニアがこれからキャリアを始めようとしている、そういうタイミングだと認識しています。会場の皆さんはまさにその世代ですよね。
少し私のAIとの関わりについてお話しさせてください。私は2010年頃、大学でAIの研究室に所属していました。当時はWebとAIの研究を行っていて、特にセマンティックウェブと呼ばれる分野を研究していました。私の研究テーマは、会計データをAIが扱いやすい形式に加工し、知識グラフに変換して、それをWeb上で公開するというものでした。
それから15年経った今、何が変わったかというと、AIが私たちの日常生活で使えるようになりましたね。当時の研究室にはロボットがあって、物を運んだり、2台のロボットが連携して水を受け渡したりする様子を見て感動していましたが、今ではそういった技術が当たり前になってしまいました。そういう時代です。
今日のスライドも含め、普段私はコードを書く時にChatGPTやClaude、Geminiなどのツールを使っています。Clineというエージェントを使ったことがある人はいますか?何人か手を挙げていますね。Clineでコードを書くのは本当に楽しいですよね。オートコンプリートが非常に便利です。また論文を読む時もGeminiをよく活用していますし、NotebookLMに研究分野の論文を入れて効率的に読むこともしています。例えば、長崎で開催された言語処理学会も先週行ってたんですが、論文をセクションごとにNotebookLMに入れて分析するなど、日常的にAIツールを活用しています。
3つのAgenda

今日はキャリアについてお話ししようと思いますので、3つのセクションを用意しました。まず1つ目が「AI時代のエンジニアリング」、2つ目が「開発現場で何が起きているか」、そして3つ目が「AI時代の成長戦略」というテーマで進めていきます。
AI時代のエンジニアリング

はい。では、まず1つ目の「AI時代のエンジニアリング」というテーマについてお話しします。まず基本的な部分として、これまでのエンジニアリングと呼ばせていただきますが、皆さんが何かを作る時にどのようなサイクルで進めていますか?
例えば「翻訳ツールを作りたい」とか「サークル内のメンバー管理アプリケーションを作りたい」など、様々なアイデアがあると思います。そういったものを実現する際、どのようなプロセスで作っていくか、少し考えてみましょう。

一般的には、まず「やりたいこと」が最初にあって、それについてインターネットで検索して調べますよね。そして実際に作ってみる段階では、APIドキュメントなどを読み、いろいろな要素を組み合わせて、コードを書いてみます。それを動かしてみて、問題があれば修正し、「ちょっと違うな」と思いながら再考し、さらに新しいアイデアが湧いてくる。このようなサイクルがあったと思います。これは、これまでもそうですし、基本的な流れとしては今後も変わらないでしょう。
で、今日のポイントの1つなんですけど、これからのエンジニアリングという中で今後何が起きるかというと、これまで説明したすべてのプロセスをAIと共に実行するということです。これは皆さんの中ですでに実践している人もいるかもしれませんが、開発の現場では圧倒的に変化が起きていることです。

先ほど、プログラミングする時にAIを使っていますか、ChatGPTを使っていますかという質問をしましたが、AIの活用は単にコードを生成してもらうだけではないんです。例えば、OpenAIのChat Completion APIでチャットボットを作るコードが欲しいと頼めば、AIがすぐに生成してくれますよね。でも、それは「コードを書く」という限られた作業、つまり「作る」という部分だけの話ではなくて、 このエンジニアリングのサイクル全体において、どうやってAIと一緒に協力していくかが重要になってきている時代 なんです。
そもそも「何をするか」というブレストの段階から、AIと一緒に考えることができます。すでにAIを壁打ち相手にしている人もいるかもしれませんが、この部分をさらに磨き込んでいくことが重要です。また、動いているコードやプロダクトに対して、AI自身がそれを検証して「本当に動いているのか」を確認したり、実際に画面を操作したりすることもできるような時代にすでに突入しています。
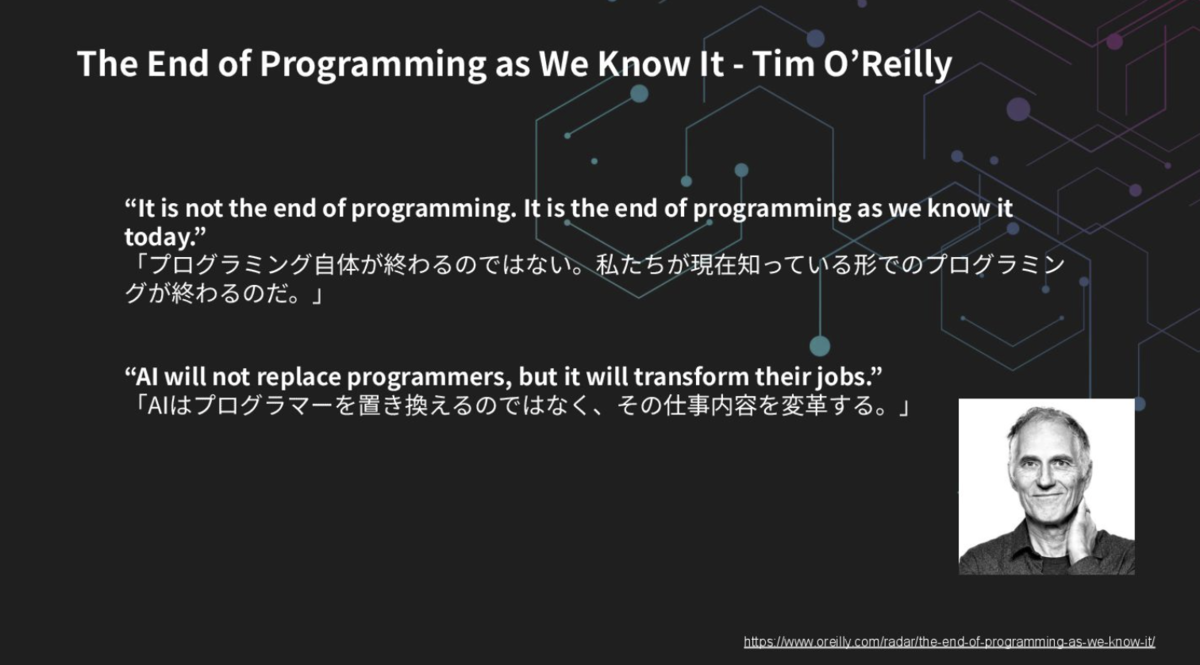
僕のね、すごく好きなあのこれ記事だったんでちょっと1つ紹介したいんですけど、Tim O'Reilly -The End of Programming as We Know Itっていう記事があって、これTim O'Reillyっって人が書いてるんですけど、Tim O'Reilly知ってますかね? O'Reilly本って聞いたことあると思うんですけど。このTimさんはすごく技術業界を俯瞰して見る良い記事をたくさん書いているので、ぜひ皆さん機会があれば読んでみてほしいと思います。
その中で特に印象的な2つのフレーズを紹介します。1つ目は「プログラミング自体が終わるのではなく、私たちが現在知っている形でのプログラミングが終わるのだ」ということ。そして2つ目は「AIはプログラマーを置き換えるのではなく、その仕事内容を変革するのだ」ということです。
これはシンプルな言葉ですが、これからキャリアを築いていく皆さんにとっても、現在会社の開発現場で働いているエンジニアにとっても、非常に重要なフレーズだと思います。つまり、これまで私たちが「エンジニアリング」と呼んでいた活動のすべてのプロセスにAIが入ってきて、その影響を受けないということはもはや不可能なんです。すべてのエンジニアがAIの影響を受け、その仕事のやり方を受け入れて、自分たちの働き方を変えていかなければならない。これが、今のAI時代におけるエンジニアリングの本質です。
開発現場で何が起きているか 〜CARTAの例〜

では、これからキャリアを築いていく皆さんが何を考えていくべきかということを少し考えていきたいと思います。せっかくなので今日はCARTAでのエンジニアリングの現場で何が起きているかということを少しかいつまんでお話ししようと思います。
CARTAの現場で実際に使われているAI
もちろん、いろんな開発の現場があります。今日の技育祭にもいろんなブースが出展されていて、さまざまな会社の方が話をしています。ですから、これはあくまで一つの例だと思ってもらえれば全然構いません。でも皆さんのキャリアにとって、これから先何が起こるのかを考える材料にしてほしいなと思って用意してきました。
私たちが今何をしているかというと、先ほど言ったように20以上の事業があって、エンジニアが170人いる中で開発チームがそれぞれ分かれているんです。そんな中でもほぼ全てのエンジニアが、AIが出てきた時代のエンジニアリングをどうしたらいいかを考えながら仕事をしています。そういった状況の中で、本当にいろんなツールの検証を社内のチームで色々始めています。

まず、GitHub Copilotですね。使っている方も多いかもしれないと思いますが、コードの補完ができます。チャット機能もありますし、最近はエディット機能も追加されたので、かなりシームレスに、特にVS Code上での体験がかなり向上してきています。一方で、下に書いたDevinやCursorといったツールは、最近名前を聞くことも増えてきていると思います。特にCursorはAI特化型のエディタで、CARTAではエンジニアだけでなく、エンジニア以外の職種の人たちもCursorを使って文章を生成したり編集したりということを始めています。
Devinについては聞いたことがない人もいるかもしれませんが、いわゆる「AIチームメイト」と呼ばれるツールです。Slack上にDevinというアカウントが入って、「Devinさん、このGitHub Issueのパッチ書いて欲しいんだけど、アプローチ考えてくれない?」と頼むと、「はい、こんなアプローチでやろうと思うんですけどどうですか?」と提案してくれます。「OK、じゃあ1番のパターンで実装して」と言えば、実際にプルリクエストを上げてくれるんです。このように仮想人物としてDevinがいて一緒に仕事をするという世界が、すでに一部の部署では実現しています。ただ、まだ基盤モデルの性能がClaude 3.7などと比べるとそこまで高くないので、全てのチームで使われているわけではありませんが、そういった体験が少しずつ始まっています。

あと、GitHub Copilot は現在パブリックプレビューで、レビュアーとしてアサインできるようになりました。普段プルリクエストベースで開発していると、レビュアーをアサインすることがあると思います。そこでCopilotをレビュアーとしてアサインできるようになり、何が起きるかというと、プルリクエストのコードに対してCopilotがコメントしてくれるようになります。例えば「ランダムグリーン」という名前がミススペルではないかとか、「G」が出ているよといった単純なミススペルの指摘だけでなく、機能に踏み込んだレビューもシームレスにやってくれるようになっています。

つまり今何が起き始めているかというと、AIがコードを書き、AIがコードを読む時代が来ているのです。
「人間はいらないのでは?」
と思うかもしれませんが、実際には完璧ではないものの、プロダクション環境でのコード開発において各エンジニアの仕事はすでにAIの影響を受け始めており、かなり楽になってきています。一方で、その空いた時間でより質の高い仕事をすることが求められるようになっています。これからのエンジニアはAIとどう関わるべきかということが、まさに今の課題となっています。
CARTAの事業におけるAIの影響

私たちは事業を作っているので「AIの影響はエンジニアリングの世界だけが受けるのだろうか?」という問いについて社内でよく話しています。CARTAの事業をいくつか並べてみると、今どんな事業でもAIの影響を受けない事業はありません。これは、みなさんがまだエンジニアのキャリアや自分自身の個人のキャリアについて考えているかもしれませんが、 さまざまな事業がそもそもAIの影響を受けざるを得なくなっておりもう逃れられなくなっています。
例えばCARTAには「コトバンク」というサービスがあり、辞書のようなサイトですが、言葉を扱うサービスですから当然AIの影響を受けます。では、どうするかというと、そもそもそのサービスを作るのに、辞書を編集する際にAIをもっと使えないかというように、プラスの方向にAIを活用していきます。また「テレシー」というCM支援のサービスもありますが、これもマーケティングのデータをたくさん受けて、どんなCMを作ったらいいか、どこに出したらいいかを考えるわけですが、データとAIを組み合わせてそういうことをやっていきます。このように、 さまざまな事業のデータを活かすためのAI、それをどう活かすべきかを考えるのが、特にエンジニアがやるべきこと だと考えています。

これまでも社内ではAIに近い領域の事業はいろいろやってきました。広告配信でこの広告を出すとどれくらい良い効果になりそうかを予測したり、CMの効果の話などもそうですが、この影響はもう避けられないと考えています。それによりこれからは生成AIで加速していくと思いますし、使いやすくなっていっていると思います。
では、事業ではAIの影響を受けるけれども、個人としてのキャリアはどうかというのが、今日のセッションの本題になります。
AI時代の成長戦略

AI時代のプログラミングがこのように変わるということ、そして事業では事業自体もAIの影響を受けて、その事業自体を変えなければならないようなことが起きているという環境の中で、皆さんはこれからキャリアを進めていくことになります。そういう中でどうしていけばいいかという話をしていきます。
深い要求に身を置く
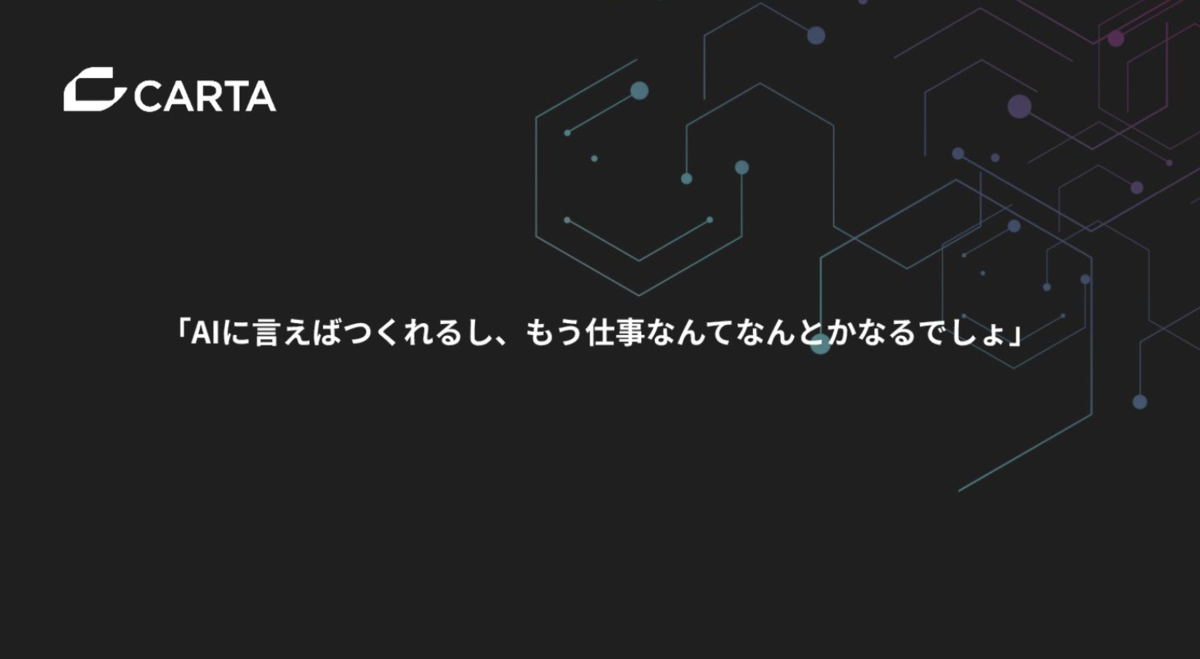
まず、 ポイントは「AIに言えば作れるし、もう仕事なんてなんとかなるでしょう」という考え方 です。いや、そんなことを言った瞬間に、もう誰がやっても同じ世界になりますよね。

絶対にそうではないし、そう言われたら負け なのです。だからそうではない。とはいえ、何をしていけばいいかというのが、多分みなさんが今これからキャリアを作る上で考えていることだと思います。
もしかしたらこれを危機に感じている人もいるかもしれませんが、一番経験の浅いエンジニアとして現場に入って、でもAIがバリバリにコードを書いていて、コードを読んでいるという環境があります。「誰も教えてくれないのでは?」と思うかもしれませんが、みなさんはむしろそういう関係に今から飛び込もうとしているのです。
みなさん自身がAIネイティブなエンジニアでもありますが、すでに現場ではそういうことが起きています。 その中にどのように入っていって、自分のレベルを連続的に上げていくかということが求められており、そのように環境を捉えるといいのではないか と思います。

私が思うこと、そして社内のエンジニアメンバーによく伝えることですが、「深い要求に身を置こう」ということです。
まず浅い要求と深い要求とは何かというと、本当に簡単な仕事、例えば「アプリを作って」というような簡単なタスクリストを作ることは浅い要求 です。今みなさんが想像できるように、頭の中のChatGPTを動かしてもらえば、Reactのコードが脳内で生成されるでしょう。もう(AIにお願いすれば)作れてしまうのです。Clineなどを使っていると、サーバーも書いて、サーバープロセスを立ち上げて、Nodeコマンドを伝えて、ブラウザを立ち上げて、ブラウザのデバッグまで全部実況してくれて、5分でできるという世界になっています。それはもう浅い要求の世界になっているのです。
しかし、例えば「従業員全員が使えて安全で使いやすくて、Google Workspaceと3つ結合して、Audit logも取れて」というように、要求が増えて複雑になり、さらに利用シーンもさらに深くなっていくと、やはりすぐには作れません。そもそもその 要求自体が分からないというような、やりたいことや欲求、要求を磨くことが人間の仕事だと思います。だから、そういう深さのある要求に身を置いて欲しいと思います。そこに成長機会が絶対にあります。
浅い要求はむしろ成長しないどころか、多分みなさんが仕事に就いた時にはもうないかもしれません。だから、 もう今からみなさんはより深い要求に、明日からでも今日からでもいいから身を置いて、「これはAIだけではできない」というものを探して探求して、もっといいものを作ろう、もっと要求をもらおうということをやっていかないと厳しい と思っています。 これはめちゃくちゃ大変だと思います。正直、多分10年前の新卒、私などは10年以上前ですが、もっと前だったと思いますが、みなさんはむしろこれを今からやっていかなければいけなくなっているというのは、結構ハードモードだと思います。

深い要求について、もう少し説明すると、私自身の経験では、いろんな経験をしてきましたが、一言で言えば
パッとどれが正解なのか分からなくて、多くの要素に合わせてリスクを見積もって意思決定して、さあやるぞとなっても、なおそれを正解に変えるためのハードルが高いような状況・状態・ケース
それ自体が深い要求に身を置いているということかなと思います。だから、自分が何かものを作る時に、この一触即発の関係にいるかどうかというのを、ぜひ自分の中で振り返って欲しいと思います。
例えば、私が昔広告のサービスをやっていた時は、サービスを落としてはいけない、落としたら一気に数百万円を失うような状況でした。そんな中で複雑な機能を組み込まなければいけなくて、でも保守性も高くしなければいけなくて、人もあまりいないという状況でした。そういう状況はやはりすごく複雑で難しかったのですが、そういう環境に置かれた後は成長するのです。自分のコンフォートゾーンではなく、ラーニングゾーンに足を突っ込んで、今はできないけどできるようになるということにチャレンジしたというのは、今こうして話していますが、当時はやはりすごく不安でした。でもそれを乗り越えていったから今があるのかなと思っています。
要求されて壁を超えて実現しようとする時に、人は成長する

深い要件に身を置くコツは、他の人からレベルの高い要求をもらうことだと思います。シンプルに言えばそうです。
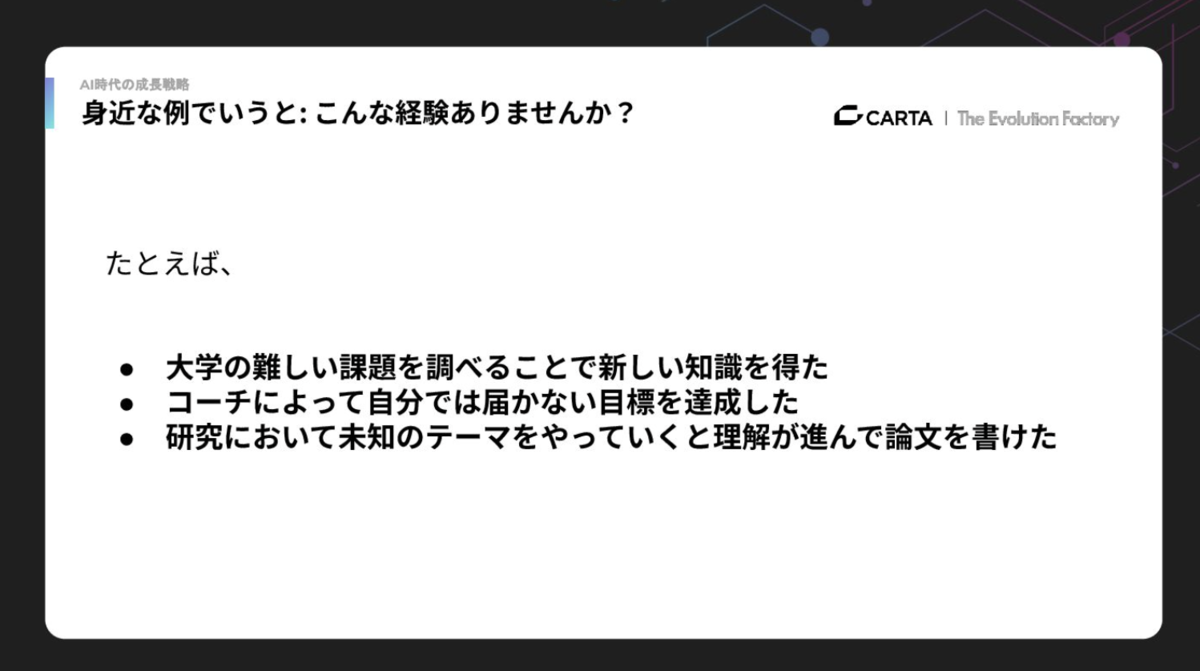
皆さんは心当たりがありませんか?
- 「これは難しいな」という課題を来週までに出せと言われて、大学でやってみたら動いた
- 部活のコーチに「お前は100メートルを12秒で走るんだ」と言われて、フォームから調べて練習して、結果的にすごく速くなった
そういう経験が皆さんにもあると思います。AIの話を聞きに来たのに突然体育会の話になったと思う人がいるかもしれませんが、本当にそうなのです。他の人からの要求というのは、それをこなそうという責任感があります。
様々な要素が働いて、人は成長していくものです。AIと向き合って便利だからとか、学びが加速しているからといっても、他の人からの要求や期待に応えるということは、非常に皆さんを成長させることだと思います。このように自分では想像できないこと、大体自分が考えることというのはパッとできそうなことや想像できる範囲になってしまうのですが、自分ではそんなこと想像もしなかったということを要求されて、自らチャレンジするということが非常に大事だと思います。

要求されて壁を超えて実現しようとする時に、人は成長します。
皆さんそれぞれに「これは壁だな」と思っていることがあるでしょう。例えば「このアプリケーションは今の自分には作れないな」とか、「このクラウドをまとめて使うのは自分にはできないな」とか、「この電子回路の設計は自分では今は難しいかもな」など、色々あるのではないでしょうか。その壁、自分が持っている壁というものにチャレンジしていかないと超えられませんし、その壁を超えるためのおすすめは、他の人から壁を超えるような状況をもらうということです。そうすると超えやすくなります。
判断力を磨いて意思決定力を高める

さて、少し視点を事業の方に置いて話をすると、事業という現場で何が起きているかというと、実はこの深い要求、つまりいろんな人がパッとやろうとして難しくて、多分解けないだろうなとか、めちゃくちゃチャレンジングだなとか、やってみても正解かわからないなと思うことというのは、実は事業においては結構プラスになる可能性が高いです。なぜなら、他の人ができないから です。そういうことができるチームというのは、やはり伸びるし強いし成長します。
キャリアの中で皆さんはこれからキャリアを選択していくと思いますが、その会社や事業、チームがどんなチャレンジをしているかということを見抜くということもめちゃくちゃ大事です。そういう環境にいると、やはり皆さんの経験が持続的に伸びるきっかけになると思います。逆に経営している場合は、いかにしてこの高い要求や深い要求というものに直面させ続けるかということがとても大事です。簡単だなと思うことだったら、絶対に競合に負けてしまいます。だからそれを導き出すということを非常に重視しています。
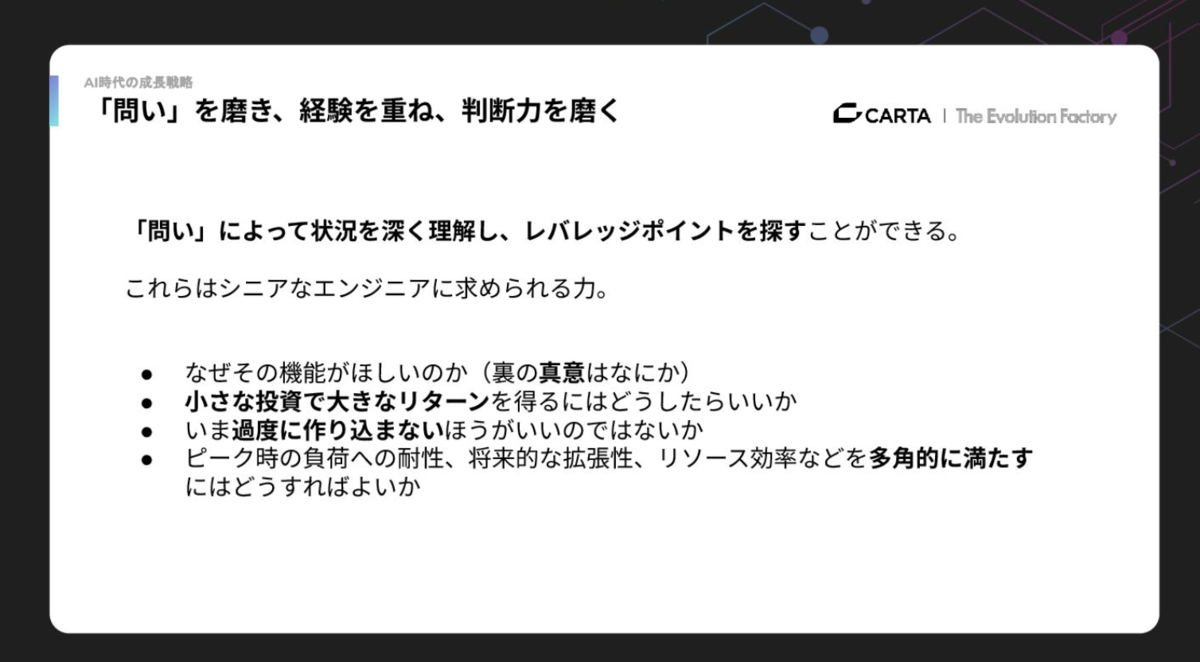
ここは少し難しいかもしれませんが、今日お話ししたかったことです。「問い」を磨き、経験を重ねて判断力を磨くということは、エンジニアにとって非常に重要な力 です。よく「レバレッジポイントを探す」と言いますが、その機能が何のために必要なのかとか、そもそもこの開発期間の投資で大きいリターンを得るにはどうしたらいいかということとか、あるいは逆に作り込まないで作るにはどうしたらいいかとか、そういう判断軸を交えながら、良いパッチを書くというのがエンジニアの仕事なのです。
この判断力というのは、シニアなエンジニアになるとものすごくズバ抜けています。皆さんがキャリアを歩んでいく中でエンジニアとして価値を高めようとするなら、この判断力を磨いて意思決定力の高い状態にしていく必要があります。ここに到達してほしいと思っています。
先ほどAIからも人からも引き出すと書きましたが、重要なことは「なぜこれをするのか」ということや「なぜこのアーキテクチャーなのか」ということを自分の言葉で話して、AIからも人からもより良い力を引き出すということです。
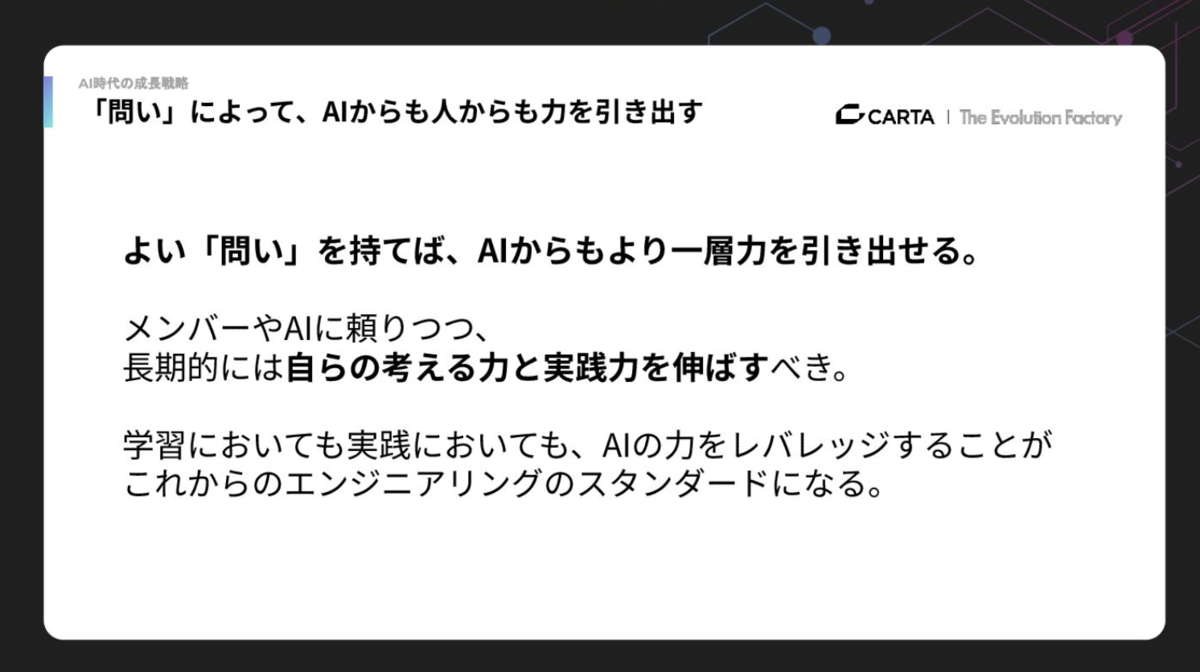
そのためには、今までの自分の経験や考えてきたことをちゃんと言語化して相手に伝えることが大切 です。そうすると、成長というのは自分だけではなく、チームメンバーやAIにも頼っていくことになります。そして長期的には、実践を続けることがこの「問い」を作る力を高めます。
今、コードをAIで書いているという方は、さっき聞いたら結構な人がやっていましたが、これは何か一時的な行動ではなく、持続的な取り組みに変えて、自分の「問い」を磨くという観点で捉えてほしいと思います。
経験を加速するフルサイクル開発

また、「経験を加速するフルサイクル」と書きましたが、CARTAホールディングスではフルサイクル開発というのは全エンジニアが実践するエンジニアリングのスタイルとして推奨しています。これは自分で考えた機能を設計して、実装して、テストして、本番環境に展開して、運用して、サポートして、そしてまた改善するところまで、自分自身で一つの機能を一貫してデリバリーするということをやっています。なぜこれをやっているかというと、経験が加速して、オーナーシップが増して、非常に質の高いものが持続的に作れるようになるからです。

これは皆さんもこれからキャリアを考える中で頭に置いておいてほしいのですが、AIが入った以上、全員の開発速度が加速します。皆さんも加速するし、経験も加速します。
素早く失敗して、より早く成長できるようになります。
いかにこのサイクルを、皆さんが機能を作っていく中や授業の中で早く回せるかが、これからのキャリアにとっての勝負だと思います。技育祭のハッカソンなどもそうですし、いろんなものづくりをやっている人もいるかもしれませんが、このサイクルをたくさん回すということを、ぜひ意識してみてください。

というわけで、未来のエンジニアリングの実践者になろうということで、皆さんに今日お伝えしてきました。

トークをまとめると、AIによって本当に考える時間、作る時間が短縮されていますし、皆さんは本当に単純なタスクがない環境に入っていくと思います。でも、今のうちから経験して素早く失敗して「問い」の力を高めることによって、エンジニアリング力がどんどん上がっていくということが実現できるのではないかと思っています。

というわけでトークとしては以上ですが、ちょっと宣伝もあるので、インターンシップ「Treasure」をやりますので、ぜひ興味ある方は応募してください。

サポーターズのインターンランキング2位です。あとブースでタイピング速度1位の人にHHKB Studioを差し上げていますので、ぜひ遊びに来てください。
以上で今日の発表を終わります。
サマーインターン「Treasure」募集中!
「深い要求」をクリアして進化したいエンジニア募集中!
※: この記事はサポーターズに許可をとった後に公開しております。



