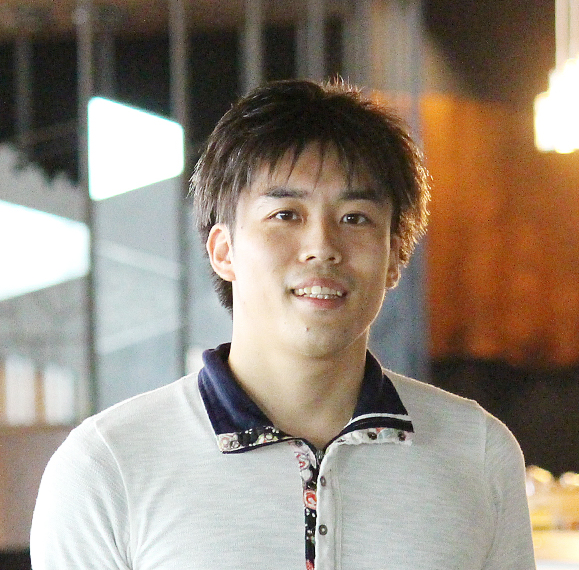はじめに
今回は、CARTA HOLDINGSの事業部Lighthouse Studioが、どのような事業を展開し、技術的な取り組みをしているのかインタビューしました。ゲームメディアとECメディアを同時に展開するLighthouse Studioについて、エンジニア3名のお話をお楽しみください。
前編では、事業部全体の技術領域を担うCTO 海老原にLighthouse Studioの全容を聞きます。後編ではゲームメディアとECメディアを担当する2名のエンジニアにそれぞれの取組について詳細に聞いています。
この記事の登場人物
海老原 昂輔 (co3k)
2014年 株式会社VOAYGE GROUP(現: CARTA HOLDINGS)に入社後、複数の新規事業開発に参画。2017年 VOYAGE Lighthouse Studio (現: Lighthouse Studio) 創業より CTO として神ゲー攻略などのメディアの運用、開発を主導。
Lighthouse Studioの事業概要
-- まずはLighthouse Studio全体の事業概要について教えてください。
Lighthouse Studio では、現在、国内向けゲーム攻略サイトである「神ゲー攻略」の運用を中心とする「ゲームメディア事業」、 Kaubel や神ゲーECなどのコマース領域事業を展開する「コマースメディア事業」、ゲームのファンコミュニティの創出・醸成をおこなう「インフルエンサーマーケティング事業」など、多方面の事業を執り行っています。特に主軸となっているのは「ゲームメディア事業」と「コマースメディア事業」のふたつのメディアビジネスで、領域や性質の異なるメディア群を、それぞれ専属のエンジニアに手がけてもらいながら、単なる記事配信に留まらない価値提供を行っているところが大きな特徴です。
別領域のメディアが相互作用で進化していく
-- 「ゲームメディア事業」と「コマースメディア事業」の領域や性質が異なるというのは、具体的にはどういうことなのでしょうか。
両事業は事業領域、規模、キャッシュポイントなど相違点が数多く存在するのですが、メディアを中心としたビジネスである点や、ライターから生み出されるコンテンツ品質やカバレッジが鍵を握る点など、共通点もあります。こうした共通点を軸としながら、たとえば先輩である「ゲームメディア事業」において試行錯誤の末に行き着いた施策や解決策を「コマースメディア事業」ではさながらタイムマシン経営のようにして取り入れたり、反対に、規模もまだ小さく新進気鋭の「コーマスメディア事業」にて機動力を活かして取り組んだチャレンジを「ゲームメディア事業」ではベンチマークとしていく 、ということが行われています。こうした動きができるのも、ひとつの組織でふたつの事業を抱えるからこその強みですね。
-- おふたつの事業で、単なる記事配信に留まらない価値提供をされているとのことですが、具体的にはどのような取り組みや工夫をされていますか。
そうですね、ゲームメディア事業の場合だと、ゲームプレイに役立つユーティリティを個々のゲームタイトルに特化した形で作り込むということをやっています。ダメージ等の計算ツールや編成するパーティ等のコスト計算ツール、ガチャの排出確率をベースとしたシミュレーターなどがその好例です。コマースメディア事業においても、類似商品同士のスペックを比較検討しやすい表を記事内に埋め込んで提供しています。
ユーザーの方々が求める情報をよりよい形で届けるため、総合格闘技のように様々な手段を用いて妥協することなくこだわることができるというところは、まさに専属のエンジニアチームがいるからこそ できる取り組みと言えるかもしれません。
全員が全部を見るエンジニア文化
-- 専属のエンジニアがいることで、多彩な取り組みが可能になっているとのことですが、エンジニア組織として大切にしている文化や取り組みについて教えていただけますか。
まず、各事業において、「全員が全体を見る」というのをすごく大事にしています。要するに、機能や業務に固定化された特定の担当を付けずに、全員が流動的に担当するということにこだわっています。これによりチーム内での知識共有を前提としたプロダクト開発が実現されやすくなったり、その時その時の状況に応じて柔軟に取り組む施策を切り替えていくといったことが可能になっています。
-- このような組織体制を実現するために、具体的にどのような工夫や取り組みをされていますか。また、その中で直面した課題や、それをどのように乗り越えてこられたのか、教えていただけますか。
まずはできるだけフルマネージドサービスに頼り、安定した記事配信の仕組みを開発、運用していくことによって、個別の課題を解決していくためのアプリケーション開発に短期的に集中できるような体制を作っていました。ただ、多種多様な取り組みをパラレルに動かしていった反面、それぞれの取組がサイロ化しやすいという問題に直面してしまったため、最近では各人が担当しているプロダクトや取り組みについての設計思想のレベルからチーム全体に共有し合い、議論し合う機会を数ヶ月に一回の頻度で実施するような施策を行っています。
-- 事業部内における技術面での統一性や共通方針について教えていただけますか。また、それがどのように事業に寄与しているのでしょうか。
私たちは事業や施策にとって最適な選択肢を模索し続けており、特段統一された技術というものがあるわけではありません。一方で、特定のライブラリやフレームワークなどの「使いこなし方」を超えた一般化されたベストプラクティスや、どういった理由で要素技術を選定したか、つまり「選び方」、「考え方」について明確にするとともに共有し合い、共通の知見が蓄積されるようにこだわっています。また、全社に貫通するエンジニアリングビジョン「 CARTA Tech Vision」 や「Lighthouse Studio 開発チーム方針」を掲げ、これを共通認識とし、事業課題の解決を最優先事項としながら、柔軟なシステム提供やリスクへの積極的な向き合いを通じて、技術とビジネスをバランス良く両立させていくことで、短期的にも長期的にも事業の成長を妨げずに促進していくことを志向しています。
脇目も振らずに目の前の事業に全力で立ち向かう
-- ありがとうございます。それでは、今後の事業展開や技術的な挑戦について、どのような展望をお持ちですか。
ふたつの事業は、それぞれ別の道を前に突き進んでいるものの、交差点のようなポイントがいくつも自然発生し、お互いに刺激を受けて切磋琢磨しながら成長しています。
ですのでまず、それぞれ脇目も振らずに目の前の事業に全力で立ち向かってもらうことを大事に しています。技術的、あるいは事業的にシナジーを生めそうなポイントがあれば、開発チーム内の日々の交流においてももちろんそうなのですが、私のような立場の人間が俯瞰して見てうまくコラボレーションを促していくなど、別々な特性をもった事業を複数抱えるからこその強みを余すところなく発揮できるように心がけています。お互いがお互いの先行事例とできるように、大小様々なレベルでの挑戦をたくさん作っていきたいですね。
ただ闇雲に「挑戦する」といっても、言うは易く行うは難しという感はあるかもしれません。しかし Lighthouse Studio ではマイクロサービスでのシステム構築を基本としており、あるマイクロサービスの影響が別なマイクロサービスに漏れ出にくいよう工夫されています。また、 Blue / Green デプロイメントなど、何かあったときの切り戻しも迅速におこなえるように整備されています。 つまり、チャレンジしたときの影響が大抵の場合はそのマイクロサービスで閉じますし影響も持続しないので、「まずは試してみる」といった、比較的リスクをとった行動を採りやすいのです。これはリードタイムが短くて済むという Web システムとしての特性と、サービス全体としての整合性があまり重視されない事業特性のふたつの恩恵を受けているおかげではあるのですが、ともあれ、こうした地の利を活かして恐れることなく事業課題に立ち向かって行きたいです。
-- ありがとうございました。後編では、それぞれのメディアをリードするエンジニア2名にインタビューします。co3kさんありがとうございました。
ありがとうございました。